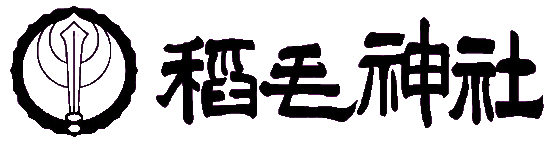祭典・祭事暦と縁市
稲毛神社の主な年間祭事です。
この他の行事はインフォメーションをご覧ください。
一月/睦月(むつき)
- 一日
-
元旦祭
一年の始めのお祭り。一番矢が授与されます。除夜祭とともに二年参りといわれています。古式勝祈祷
当社に古くから伝わる由緒深い夜のご祈祷(予約制)歳旦祭
※同日、氏子青年会によるチャリティーの他、物品・飲食品等の販売も行う場合があります。
年の始めに「天下泰平」や「五穀豊穣」等を 祈願するお祭りです。

- 一日~七日
-
有名人慈善絵馬展
画家・書家・芸能人など、各界で活躍する有名人の手による絵馬約200枚を境内に展示。
絵馬は入札制によりご希望の方へと授与され、益金は(財)毎日新聞東京社会事業団に寄託し、社会福祉事業に役立てられます。
- 成人の日
-
成人祭
成人の奉告と将来の加護を祈ります。
二月/如月(きさらぎ)
- 節分日
-
節分祭
節分祭にご参列の年男(女)の皆様には、行列行進および豆まきにもご参加頂きます。
行列行進・節分祭終了後、厄除豆まきが行われ、有志奉納の福物(景品)をお頒ち致します。
三月/弥生(やよい)
- 春分の日
-
春季祖霊祭
春分の日は、秋分の日とともに彼岸としてご先祖様の御霊(みたま)を祭り、供養します。
稲毛神社では、春季祖霊祭を行い、当神社でお葬式を行った家の方の合同祖霊祭が行われます。
四月/卯月(うづき)
- 第一日曜
-
稲荷講さくらまつり
境内社である堀田稲荷神社、第六天神社の例祭です。
稲荷講の方々主催による、出店・ビンゴ大会・奉納演芸等が行われます。
- 二の巳日
-
和嶋弁財天社例祭
稲毛神社の境内(神楽殿付近)に鎮まる和嶋弁財天社の例祭です。 - 昭和の日
-
昭和祭
昭和天皇のご聖徳ご事績を景仰し、皇室の弥栄、国家国民の繁栄、世界平和を祈ります。 儀中の舞は浦安の舞。祭典後は国旗を掲揚致します。
五月/皐月(さつき)
- こどもの日
-
子供の日祭(菖蒲祭)
次代を担う子供達の健やかな成長、国の隆昌と世界平和を祈ります。
このお祭りには、通常の神饌(しんせん:お供え物のこと)に加えて由縁の柏餅と菖蒲がお供えされます。
- 六日
-
白山神社例祭
稲毛神社の境内に鎮まる白山神社(はくさんじんじゃ)の例祭です。 - 八日
-
御嶽神社例祭
稲毛神社の境内に鎮まる御嶽神社(みたけじんじゃ)の例祭です。
六月/水無月(みなつき)
- 三十日
-
水無月大祓式
知らず知らずに触れた罪穢(つみけがれ)を祓い元気に夏を乗り越えます。
大祓式終了後、甘酒とちまきをお頒ち致します。
七月/文月(ふづき)
- 七日
-
七夕
六月中旬頃より稲毛神社の本殿前に大竹が立てられ、短冊に記された皆様の願いが大神様に届けられております。
八月/葉月(はづき)
- 一日~
-
【一日】宵宮
【二日】例祭、古式宮座式
【例祭直後の日曜日】神幸祭
稲毛神社例大祭「川崎山王祭」
一日、二日には町内神輿が町中を練り歩き、最終日には宮神輿が町中を練り歩きながら、お旅所「姥が森弁財天」へ渡御します。
また、二日に行われる、古式に則った宮座式は県の文化財にも指定されています。稲毛神社における最大のお祭り。
境内には多くの出店が並び、神楽殿では神楽や奉納演芸が華やかにお祭りを盛り上げます。
九月/長月(ながつき)
- 十九日
-
子神社例祭
稲毛神社の境内に鎮まる子神社(ねのじんじゃ)の例祭です。
子神社の社殿は総けやき作りで、現存する宿場時代の唯一の建造物です。 - 秋分の日
-
秋分祭
秋分の日は「祖先を敬い、亡くなった人々を偲ぶこと」を趣旨として制定された祝日。
宮中では、天皇・皇后・皇親を祀る「春季皇霊祭(春分の日)」「秋季皇霊祭(秋分の日)」が行われます。
また、稲毛神社でも同日12時より祖霊を祀る「秋季祖霊祭」を行います。
十月/神無月(かんなづき)
- 十日
-
金刀比羅宮例祭
稲毛神社の境内に鎮まる金刀比羅宮(こんぴらぐう/ことひらぐう)の例祭です。
本宮は香川県に鎮座し、ご祭神の大物主神(おおものぬしのかみ)は水神といわれており、交通安全(特に海上に於いて)をご神徳とし厚い信仰を集めています。 - 十七日
-
大神宮例祭
稲毛神社の境内に鎮まる大神宮(だいじんぐう)の例祭です。
大神宮には、伊勢神宮のご祭神と同じ、天照大御神(あまてらすおおみかみ:内宮)と豊受大神(とようけのおおかみ:外宮)が祀られています。 - 十九日
-
佐佐木神社例祭
稲毛神社の境内に鎮まる佐佐木神社(ささきじんじゃ)の例祭です。
佐々木四郎高綱公は源頼朝の命を受け、稲毛神社の造営奉行として改修工事にあたられました。
十一月/霜月(しもつき)
- 十五日
-
七五三詣
お子様の成長を感謝し、益々の加護を祈ります。
- 酉の日
-
酉の市
境内の大鷲社(おおとりしゃ)の例祭です。縁起物の熊手や福枡をお頒ち致します。(酉の日はその年によって変わります)
夏の例祭に次ぐ縁市。
十二月/師走(しわす)
- 二十一日
-
冬至祭
冬至は、一年の中で昼が最も短く夜が最も長くなる日です。
冬至祭はその年の冬至の時間に祭典を行います。 - 三十一日
-
大晦日大祓式
一年の罪穢(つみけがれ)を祓い清め新年を迎えます。
大祓式終了後、甘酒をお頒ち致します。除夜祭
一年の恵みを感謝する最後のお祭り。
元旦祭とともに二年参りといわれています。
古神札焼納祭
一年間お祭りしたお神札お守りをお焚き上げ致します。