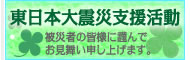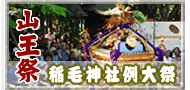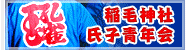参拝者の安全確保のため、また神事行事の厳粛なる斎行のため、
境内全域及び全ての神事行事中、ドローンやラジコンヘリ等、
飛行物の使用は固くお断りいたします。
ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
川崎山王祭に於ける神事
 孔雀
孔雀 玉
玉稲毛神社は景行天皇との縁を伝える川崎の古社ですが、江戸時代までは「河崎山王社」と呼ばれ、東海道川崎宿の鎮守でした。 そのまつり「川崎山王祭」の最終日には「孔雀」「玉」と呼ばれる男女2基の神輿の渡御が行われます。そこには、神の結婚、懐妊、御子神の誕生というストーリーが隠されています。
8月1日
8月1日の夕方には前夜祭(宵宮祭)が行われます。例祭に先立ち行われる前夜祭では、3日間の無事と盛況を祈念します。
8月2日
8月2日の午前中には例祭が厳粛な雰囲気の中で齋行されます。 午後には「古式宮座式」(神奈川県民俗文化財)が神主と氏子旧家の主人によって密やかに厳かに行われます。その中で玉神輿には女神、孔雀神輿には男神の御神体が遷されますが、その遷し方に古伝があり、それは神様の結婚を表しています。
例祭直後の日曜日
例祭期間最終日の早朝、神輿は氏子巡幸に出発します。古来”玉の神輿は荒れ神輿”といって、女神輿の方が担ぎ方が荒くケガ人も多いのです。担ぎ手たちは”玉神輿は御霊が入るととたんに重くなる。だから自然に担ぎ方も荒くなる”と言いますが、これは女神の「懐妊・陣痛」を表しています。
2基の神輿は夕方近くに御旅所「姥が森弁天」に着きます。ここは山王さまの御子神とその乳母の逸話を伝える地です。古い井戸から汲んだ御神水を供えて「宮座式」が行われ、終わるとその御神水を神輿にかけます。これをしないと”神輿がおさまらない”と言いますが、誕生した御子神の「産湯」です。
午後8時過ぎ、神輿は大勢の氏子に迎えられて宮入りし社殿に据えられます。境内はまつりの余韻を楽しむ人々で賑わいますが、社殿では御神体を本殿にお還しする神事が静かに行われています。
変貌の激しい川崎のまちには、歴史を伝える遺産はほとんどありません。そんな中で「川崎山王祭」は中世の遺風をたしかに伝えています。神々の結婚と誕生を表すこのまつりは、まちが地元と外来の調和のなかに生み出す新たな生命力の希求でもあります。 このまちが発展と変貌をやめない根源を、このまつりの中に見いだすことができます。
川崎山王祭のいわれ
御祭神(ごさいじん)と御社号(ごしゃごう)
稲毛神社は武神・武甕槌神(たけみかつちのかみ)を祀(まつ)る川崎の古社で、古くは御祭神の御名をそのままに「武甕槌宮(たけみかつちのみや)」と呼ばれていました。
その後、欽明天皇によって経津主神(ふつぬしのかみ)(武神)、菊理媛神(くくりひめのかみ)(和睦神)、伊弉諾神(いざなぎのかみ)・伊弉冉神(いざなみのかみ)(協力神)の四柱が合祀され、「勝」と「和」の御神徳が生まれたといわれています。
平安時代の末期、河崎冠者基家(かわさきのかじゃもといえ)がこの地を治めるようになって「河崎山王社」と改称され、さらに慶応四年、武蔵国橘樹郡稲毛庄の大社であるところから「稲毛神社」となって今に至っています。 そこで稲毛神社のお祭りは今も「川崎山王祭」と呼ばれています。
御祭日(ごさいじつ)
稲毛神社の祭礼日はもともと旧暦の六月十五日(十四日から十六日)でした。明治になって太陽暦(新暦)が採用された後も、旧暦六月十五日にあたる新暦の七月下旬の日に行われていました。
ところが、明治の末から川崎には多くの工場ができて若い労働者が急増します。彼らの賃金は月末払いでした。七月下旬の祭りのころは財布の中が寂しい、祭りはぜひ八月上旬に、という要望が強くなっていました。大正のはじめ、祭日を新暦にするとき、その要望を考慮して八月一日(前夜祭)、二日(例祭)、三日(神幸祭)という今の祭日が決められました。
いかにも働く者の町・川崎らしいいきさつです。
(註:平成24年より、神幸祭は「例祭直後の日曜日」に日程が変更されました。)
宮座(みやざ)・社人(しゃにん)と「神の結婚」
奈良や平安の時代には、地方の神社には専任の神主がいないことが多く、神事行事は氏子の代表者たちが行っていました。その人たちを社人と呼び、その制度を宮座といいます。 江戸時代になると関東にも神社や祭りが増えますが、そのころには各神社に神主が置かれるようになっていて、社人や宮座は必要がなくなっていました。ですから、由緒ある宮座が今も稲毛神社に伝わっていることは、ご創建の時代が古いことを示すたいへん貴重なことなのです。
例祭の日(八月二日)、七家九人の社人のうち「お台所役」をつとめる者は、古来よりの口伝(くでん)の方法で「麦御供(むぎごく)」(麦でつくる3種類のお供え物)と「濁酒(にごりざけ)」をつくります。特別な装束を着てそれを神様に供え、おさがりを皆で食します。このとき箸は青茅(あおがや)を用います。その後、孔雀と玉の2体の大御輿(おおみこし)に御神体(ごしんたい)をお遷(うつ)しします。この遷し方に秘伝があって、それは神様の「結婚」だといわれています。
この一連の儀式は「宮座式」と呼ばれ、かつては浄闇(夜)の中で行われ、一般の人々は参列することも見ることもできない秘式として伝えられてきました。現在、この宮座式は神奈川県の文化財に指定されています。
総持(そうも)ち・迫り持(せりも)ち担ぎと「女神の懐妊」
神幸祭当日の朝、まだ薄暗い頃、二体の大神輿は社殿を出て境内に据えられ、飾り付けが行われ、お祓いを受けて氏子23町内巡幸に出発します。巡幸の仕方は町会ごとに担ぎ手が引き継ぐのではなく、すべての行程を氏子総がかりで担ぎます。これを「総持ち」といいます。
担ぎ方にも特色があります。担ぎ手全員が神輿に背をむけ、肩から首の後ろの方で迫り上げるようにするところから、「迫り持ち担ぎ」と呼びます。神様に息がかからないようにするためとか、重い神輿を落としても担ぎ手が下敷きにならない担ぎ方だとかいわれています。そして、担ぎ手が全員進行方向を向く江戸風のかつぎかたは、駕籠(かご)や棺(ひつぎ)の担ぎ方なので「雲助担ぎ」「とむらい担ぎ」といって嫌います。
また、担ぎ棒を「リンギ」とよびますが、これも山王氏子独特の呼称のようです。おそらく、練る木「レンギ」の転訛ではないかとおもいます。 孔雀神輿(男)、玉神輿(女)の順につらなって渡御しますが、昔から「玉の神輿は荒れ神輿」といって、玉神輿は担ぎ方が荒くケガ人も多かったようです。「女神の方がたたりが強い」と説明されてきましたが、最近の研究者の説では「懐妊した女神の陣痛」であろうといいます。
勅幣(ちょくへい)と御幣持(ごへいも)ち
稲毛神社は、そのむかし「武甕槌宮」と呼ばれ、東国の平定を祈る勅願所でした。そのころ欽明天皇からいただいたという7本の勅幣が、「当社第一の神宝」として伝えられていましたが、第二次世界大戦で焼失し、今は復元したものが使われています。
神幸祭では、7人の社人はこの勅幣をもって大神輿を先導します。これを「御幣持ち」「御幣(おんべ)担ぎ」「お勅幣さん」などと呼びます。今は徒歩ですが、江戸時代の末までは騎馬でした。 当地に「御幣(おんべ)持ちのようだ」という表現がありました。些細なことに格好を付け形式張る行為や人をいったそうです。
御旅所(おたびしょ)-姥が森弁財天(うばがもりべんざいてん)
孔雀と玉の大御輿は、昼下がり、御旅所「姥が森弁財天」に詣でます。ここには二つの言い伝えがあります。 一つは、むかしこのあたりに一人の老婆が住んでいて篤く山王社を信仰し、毎朝、森の池に湧く清水を汲んで山王社の神前に供え、怠ることがなかった。老婆は死後「姥が森弁財天」として祀られ、山王社の御旅所になった、というもの。
もう一つは、むかし、海浜に姥が森という弁天様を祀る森があって、そこには新田義貞公の寄進した長さ八丁の馬場と御手洗池があった。ある日、一人の乳母が童子を連れて馬競べを見ていたところ、ふとしたことから童子が転んで片眼をつぶし、それがもとで死んでしまった。その後、この森や池にすむ蛙や蛇や魚はみな片眼になってしまった。実は、この童子は山王様の神様の子だった、とういものです。
姥が森弁財天は明治末年の小神社合祀令によって、近くの「新田神社(御祭神、新田義貞公)」の境内に移されました。また町名も「鋼管通り」と変更されたのですが、地元の人々は「姥が森町内会」と名を残し、町内会館のとなりに今も弁天様を祀り、御手洗池の跡と伝える井戸を守っています。
大御輿が、新田神社の姥が森弁財天の前に着くと、姥が森町内会の役員はその井戸から汲んだ御神水を大御輿にふりかけます。これをしないと、神様が怒って御輿が無事におさまらないというのです。近頃の研究者は、これは誕生した神の子の産湯で、姥が森は「産屋の森」ではないかといいます。
山王神輿踊り
昭和55年、稲毛神社では「山王まつり音頭」と「山王神輿踊り」という二つの歌を作り踊りを振り付けました。宮入行列の先頭はこの歌と踊りがつとめます。産土神(うぶすながみ)に新しい生命力が生まれたことを喜んで、氏子たちはこの行列を提灯で迎えます。 山王神輿踊りの一節に次のような箇所があります。
右手に末広 弓手に手丸(手丸とは手に持つ丸い提灯)
月も銀杏の 上からさして
めでためでたの お宮入り
おさめ担ぎは 社の中で
汗はわき出る かけ声しめる
引かれて帰る うしろ髪
大神輿の宮入が無事に終わり、2体の御神輿が社殿の前庭に据えられると、もう一般の人は神輿に触れることはできません。 「赤ハチマキ」「役半纏」と呼ばれる渡御の役員だけで神輿を拝殿におさめます。拝殿に据えてしまえば、もう来年まで担ぐことはできません。彼らは拝殿で流れる汗も厭わず陶酔したように担ぎます。次第にそのかけ声は涙声になっていきます。この「おさめ担ぎ」が終わると、早朝からの神輿渡御で疲れきった氏子役員も若衆も家路につきます。
還霊祭(かんれいさい)(御霊かえし)
神輿が無事に納められても境内は奉納演芸や夜店を楽しむ参詣者で賑わっています。そんな中で、社殿ではすべての扉を白絹の幕でふさぎ、神主と社人だけで御神体を御神輿から御本殿へ返す最後の儀式がおこなわれます。
それが終わると、社人の一人が勅幣の本(石突き)で参詣者の頭上を撫でるようにお祓いします。これを持って、炎天下の元で行われた川崎山王祭は執り納めとなります。
付録
「麦秋祭(ばくしゅうさい)」と芭蕉の句
関東の神社の夏祭りの多くは、江戸時代に盛んになった「疫神祭(えきじんさい)」です。暖かくなると人や作物が病気にかかりやすくなるのは疫神(悪霊)の働きが活発になるからだ。悪霊は賑やかなことが好きだというから、笛や太鼓ではやしたて、神輿や山車に積んで海や川に運んで洗い流してしまおうといのが疫神祭です。
これに対して「川崎山王祭」は守護神が新しい生命力を持つことを願う祭りであり、また、宮座式に伝わる麦御供には麦の収穫を感謝する「麦秋祭」の色彩もあらわれています。 神様へのお供え物といえば「米」です。麦を供えることは珍しいことです。川崎が永く米作より麦作の盛んな土地であったことを伝えています。 元禄7年(1694年)5月、松尾芭蕉は江戸から故郷の伊賀に帰るに当たって八丁畷の茶店で見送りにきた弟子たちと句会を開きました。
| 麦ぬかに餅屋の店のわかれ哉 | 荷兮 |
| 麦畑や出ぬけてもなほ麦の中 | 野坡 |
| 浦風や群がる蠅のわかれどき | 岱山 |
| 刈り込みし麦の匂ひや宿の中 | 利牛 |
| 麦の穂をたよりに把む別れ哉 | 芭蕉 |
東海道の松並木をはさんで、両側の一面の麦畑ではそこかしこ取り入れが始まっている。山王まつりももうすぐだ、そんな様子がうかがえるではありませんか。
「神の巡検(じゅんけん)」と「神輿の復興」
川崎山王祭のもう一つの意味は「神の巡検」ということです。一年に一度、神様が氏子の町々の様子や人々の生活ぶりを見にこられる、ということです。ですから、御神輿は氏子全町を巡幸します。そして、道々「祓い手」と呼ばれる神職が神輿の通る道と町々人々を祓い清めて行きます。
稲毛神社は、大東亜戦争の戦禍により社殿・御神輿以下ことごとくを失ってしまいました。昭和24年、御社殿の復興にかかりましたが、しばらくすると、社殿より神輿の復興が先だという意見が出だしました。「戦争でこんな姿になってしまった我々を、ぜひ神様に見てもらいたい」というのがその理由でした。
社殿より先に神輿というこの非常識な意見は次第に力を得て、翌年大神輿2体は見事に復興しました。思いの外はやい本格的神輿の注文に、「空襲の中、材料だけは必死で確保しておいた甲斐があった。一世一代のものを作らせていただきます。」という行徳の後藤神輿店の主人の熱意も、あずかって力があったと聞いていますが、「神の巡検」というまつりの持つ意味そのものが大きな力を発揮したのでしょう。
「榎さま」「榎町」
ある年、玉神輿が神社のそばの橋のたもとで大いに荒れ、深い泥田の中に落ちてしまいました。若衆たちが力を合わせ懸命に引き上げようとしたのですが、神輿は静かに沈んでしまいました。やむを得ずその場に小さな祠を祀り、目印に榎を1本植えました。 この祠は「榎さま」と呼ばれ、女性の病気に御利益があると、多くの参詣者を集めました。 「榎町」の町名の起源となったこの「榎さま」は、今も榎町の町内会の人々によって守られています。
「御所車(ごしょぐるま)」と「亀戸天神(かめいどてんじん)」
むかし、山王まつりには立派な御所車がくり出し、まつりに花を添えていました。ある年、この御所車が傷んだので江戸亀戸の修繕屋に修理に出していたところ、なんとその店が火事に遭ったのです。同じく御所車を修理に出していた亀戸天神の氏子たちは大急ぎで駆けつけ、御所車1台をようやく助け出しました。ところが、その御所車は天神さまのよりずっと立派な山王さまのものでしたから、山王氏子と天神氏子の争いになりました。しかし、いずれ助からなかったであろう御所車ですから、最後には気持ちよく天神さまに譲ってしまったそうです。 この話は、江戸時代に川崎宿で起こったエピソードを綴った「あまのさへすり」という本にのっています。
佐藤惣之助(さとうそうのすけ)「祭りの日」
川崎の生んだ詩人・作詞家の佐藤惣之助は山王祭りを愛し、いくつかの歌や詩に詠み込んでいます。最後に、惣之助の「祭りの日」という詩をご紹介しましょう。
祭りの日は佳(よ)き哉(かな)
一重の紅罌粟(イギリスぼたん)の如し
殊に明日(あす)の祭を愉しみて
青き頭髪(かみ)刈る匂ひは更に懐かし・・・
空は碧玉なり 紅き提灯をつらねよ
青竹の笛吹けば 月はのぼり
つねに恋しき幼き人の あえかに粧ひて
海酸漿(うみほおずき)の匂ひほのかに
茜する都の方より来る時なり・・・
夕べとなれば幼同志(おさなどち)
あまき檸檬(レモン)水ねぶりて
怪談めきし宮の杜に
異国風の見世物を観る
クラリネットの音ぞ たへがたくかなし・・・
祭の日は佳き哉 幼き唄ぞ
されど過ぎては昨日の笛なり
いみじくも水の嵐に流れさり
老いてぞ今はなかなかに
待つべき術もなからめや
この詩の碑は惣之助夫妻生誕100年を記念して、昭和六十二年に川崎今昔会によって稲毛神社境内に建立されました。